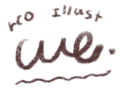デザインソフトを触る時間は「少しだけ」?クオリティを高める制作フロー
この記事では、デザイナーが成果物のクオリティを担保するために大切な、「アイデアを練る時間を確保する」そして「検証する」ことについてご説明しています。
時間がない時は、手を動かしたほうが早い気がするけど、たいていなんのひねりもない、要素を並べただけの成果物が生まれ、結局だし戻しが増える。
忙しい時ほど、アイデアを捻り出す工程に時間をかけたいものです。

最近、押し流されてしまいそうなため、平時の自分がどのようにデザインをカタチにしていたか記録しておきます。
もくじ
この記事でわかること
- デザインソフトを触る時間は「少しだけ」な理由
- 制作以外の前段階でやること
- 作業工程ではなにをするの?
依頼者側(ディレクター)が得られるもの
靴屋の小人ばりに知らぬ間につくってくれてるような気がしますが、デザイナーは制作工程で、どのようなことをしているのでしょうか。
記事を読み終えたら、依頼しやすくなってるかも?
制作全体の流れについては、こちらの記事がおすすめ
アイデアを練る①原石集め
商業デザインには目的があります。

自分の趣味や世界観を表現するのではなく、誰かの目的を叶えるために、イタコ気分でアウトプットする。これがデザイナーの仕事だと考えています。
①-1【調査】ペルソナ・ターゲットの理解「判断材料を集める」
当然ながら霊を呼び寄せることはできませんので、推理するための材料が必要です。
古本屋から一歩も動かずに推理する京極堂や、死因を特定する検屍官のように、まずは情報を得ることから始めます。
この商材を好む人たちは、
- どのようなデザインを目に留めるかな?
- どのような生活をしているのかな?
- どのような趣向なのかな?
- 普段はどこで何をしているのかな?
- どんなときにスマホを触るのかな?
- どんな悩みがあるのかな?
- 解決するために、いくら投資できるのかな?
- 代替案は何かな?
集めれば集めるだけ精度が上がるわけじゃないけど、ターゲットと自分の属性が違うときは、ある程度理解を深めておきたいものです。
①-2【要件確認】サイズや仕様を確認し、掲載要素を決める
媒体によって目的や面積が違うため、一概に項目が決まっているとは言えません。しかしながら、目的を果たすためには、言葉・イメージなど、なんらかの媒介が必要です。
必須要素について、決め打ちすることが大切です。
たいてい、事業主側は伝えたいことが溢れてしまうものですが、余すことなく伝えたら理解してもらえるか? というと、そんなことないんですよね。
相手に合わせて、情報の粒度、訴求ポイント、表現は変わるものです。これらを精査することは、かなり大切だと言えます。
デザイナーの立場では、ある程度精査された情報に触れることが多いのですが、さらにクオリティを上げるために、デザイナー目線で情報を磨いてあげたいものです。
アイデアを練る②石の魅力が引き立つカットを探る

さて、ここから具体的なお話になります。
②-1【調査】競合や参考デザインピックアップ
みんな大好きSNSやPinterest、雑誌などをみながらイメージに近いデザインをピックアップしておくよ!(あくまでも参考用)
②-2【トンマナ策定】形容詞を書きまくる
集めた情報をベースに、「こんな雰囲気」を言語化していきます。
いちど言語化してから、再構築することで「気付いたらパクってた!」を防ぎます。

②-3【トンマナ策定】ムードボードつくる
②-2で整理した形容詞を表すためにはどんな雰囲気がいいかな? 近しいイメージを集めます。
配色・形状・書体・質感・レイアウト(雰囲気)・シチュエーション・合いそうなモデル
などを1枚の紙(PPTなどのアプリの上)にまとめておくと、立ち返りやすいです。

クリエイティブ制作の進行にお困りの方は
ムードボードや形容詞を使ったトンマナのすり合わせがおすすめ!
アイデアを磨く①手を動かし探求する

サムネイルを書いて検証(デザイン案のたたき台)
サムネイルとは、親指の爪くらい小さなラフのことをいいます。
①-2で洗い出した要素のレイアウトをざっと書いて検証します。
不足要素がないか? 見せ方に違和感がないか? サムネイルの段階で、検証してしまいましょう。
絶対にこれはないわーー! というものは清書せずに省きます。
▼ひとことアドバイス
要素の色や形書体配置がわかるようにすると検証しやすいですよ。
サムネイルの書き方に決まりはありませんが、枠の比率を制作物と合わせておいた方が制作時スムーズです。

デザインツールさわるよ!(清書)
サムネイルを考えた後に、やっとデザイン作成ツールを触ります。
Photoshop、Illustratorのようなアプリケーションでデザイン制作します。
清書です! アイデアがより輝く磨きかたを探ります。
まずは、福笑いみたいにアートボードに要素を全て並べてください。
並べた要素をサムネイルを見ながらレイアウトし、違和感のあるところは調整していきます。
▼ひとことアドバイス
複数の要望がある場合や迷いがあるときは、「こうしたらどうなるだろう?」を検証する目的で複数案を作成します。要望Aに寄せた案、要望Bに寄せた案、折衷案のように複数トーンをつくり、検証すると良さそうです。
さらに細かい粒度でデザイナーの作業内容を知りたい人は
デザイナーがアイキャッチ・バナー制作時に気をつけていること、の記事がおすすめ。
アイデアを磨く④作成した案を検証する
作成した案をもとに、デザインの検証を行います。どれだけ検証・確認の工程に時間をかけたか? が、デザインのクオリティを左右すると言えます。
以下の観点で検証し、デザイン提出時に制作意図説明として、添えるようにします。
- ペルソナが「自分ごと」と捉えるトンマナになっているか?
- デザインに意味づけができてるか?
→どうしてそのカタチ、色、書体、質感を選んだのか? - 予定通りの優先順位で視線の誘導ができてるか?
- 実際の使用場面で見たときに違和感ないか?
▼ひとことアドバイス
のめり込むと視野が狭くなるものです。一晩寝かせる余裕があると尚よし。
デザインを作っているうちによくわからなくなってしまった時は、一度時間をおいて見返したり、離れて見てみたり、実際の投稿画面に当てはめて確認すると、判断しやすくなりますよ。
アイデアを磨く⑤理由を言語化する
④の検証内容をもとに、なぜこの磨き方を選び、このカットにしたのか、言語化して提出できると尚よし。
意図を見せることで、第三者の目を通して、良さや違和感に気づけるチャンスです。

アウトプットを見ただけでは、あなたの意図は伝わらないことの方が多いものです。蛇足だと思っても、無粋だと思っても、提出時にはコメントを添えるとよいですね。
まとめ:工程・省くべからず
ダイアの原石を探し、磨き上げて、美しさが最大限に活かされるカットを施すためには……
↓
情報を収集し、イメージを膨らませてから、手を動かし、検証を怠らない。
マンガ家さんは、果たしてネームを書かずにラフを描くのでしょうか?
下書きをせずペン入れして清書するのでしょうか?
漫画と比べたらデザインは、アイデアを練らなくても、ソレっぽく作ることが出来るかもしれません。しかし、クオリティが落ちることは必至。工程を省かねばならない状態でギリギリ回しているなら、それはもうアウト。出涸らしのお茶を量産するようなモノ。
クオリティを担保する意味でも、線引きすべきだと改めて感じたのでした。

工程省くべからず。
いつも、名探偵になった気持ちで仕事しています

Web業界の片隅に生息しているマダムです。肩書きは特にありませんが、コアスキルはデザイン。(当ブログでの発信内容は、個人の見解であり、所属組織とは一切の関係がございません)